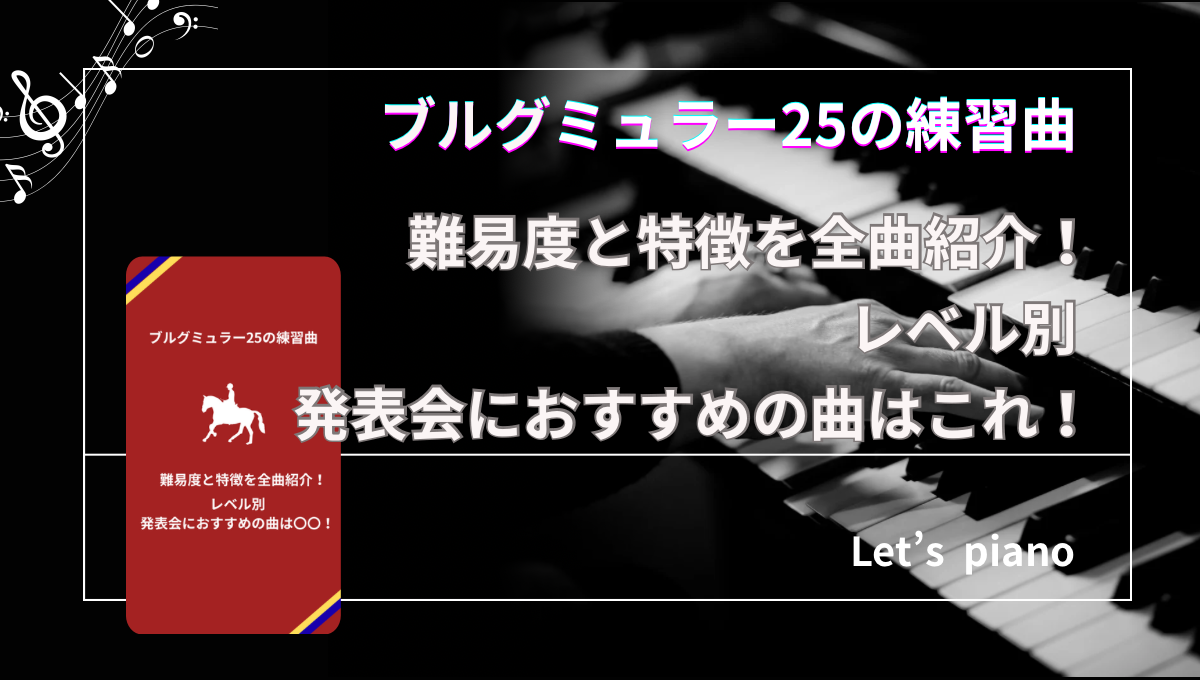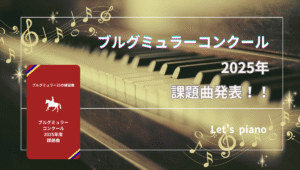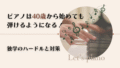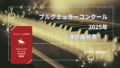発表会でブルグミュラー25の練習曲の中から選んで演奏することになったけれど、娘に合うレベルの曲が全然分からない!

上手な子たちはブルグミュラーの「タランテラ」を練習しているけれど、わたしが弾ける「素直な心」と同じくらいの難易度なのかな??
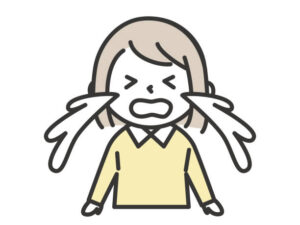
4年生になるけどなかなか「清らかな流れ」が上手に弾けない。
みんなもっと難しいのを弾いているのかなあ・・・。
こんなお悩みありまありませんか?
この記事では
- 【ブルグミュラー25の練習曲】全曲の難易度と特徴
- 発表会で人気のある曲
- 生徒や先生に人気のある曲
など詳しく書いています。
きっとあなたにも好きな曲や、目標になる曲が見つかりますのでぜひ最後までご覧ください!
※ブルグミュラーコンクール2025年の課題曲と入賞しやすい曲についてはこちらで詳しく解説しているので、興味があればぜひご覧ください。
【ブルグミュラーコンクール2025年】課題曲まとめ!曲選びのポイント必見!!
【ブルグミュラー25の練習曲】の教本は色々ありますが
もし練習するのが小学生ならこちらの本がおすすめです。
コードネーム、和音記号が付いていたり、子供でも踏みやすいペダリングにもなっています。
また、全曲譜めくりせずに見れるよう見開きになっていますし解説も分かりやすいです。
私も今から買うなら絶対これが良い!
詳しく知りたい方はこちらのサイトで詳しく載っています。

この記事を書いたのは
ピアノが大好き!
ピアノ研究科「to-ko」です。
我が子がピアノを習い始めた事をきっかけに
自分も大人の初心者「独学ピアノ」として始めました。
前向きに取り組んでいるおかげか
娘は出場させていただいたコンクールでは軒並み賞をとれるくらいに上達しています!
同じく頑張る独学ピアノさんや、
お子供のサポートに奮闘中のママさんの、
少しでも参考になる情報をいち早くお届けします!!
- ブルグミュラー25の練習曲【難易度】・【特徴】
- ブルグミュラー25の練習曲の「練習する時のポイント」全曲紹介
- 1番・「素直な心」(La candeur)
- 2番・「アラベスク」(L’arabesque)
- 3番・「牧歌(パストラル)」(La pastorale)
- 4番・「小さな集会」(La petite reunion)
- 5番・「無邪気」(Innocence)
- 6番・「進歩」(Progres)
- 7番・「清らかな流れ」(Le courant limpide)
- 8番・「優美」(La Gracleuse)
- 9番・「狩り」(La chasse)
- 10番・「やさしい花」(Tendre Fleur)
- 11番・「せきれい」(La Bergeronnette)
- 12番「別れ」(Adieu)
- 13番「なぐさめ」( Consolation)
- 14番「スティリエンヌ」(La Styrienne)
- 15番「バラード」(Ballade)
- 16番・「あまいなげき」(Douce plainte)
- 17番「おしゃべり」(La Babilarde)
- 18番「気がかり」(Inquietude)
- 19番「アベ・マリア」(Ave Maria)
- 20番「タランテラ」(La Tarentelle)
- 21番「天使のハーモニー」(L’harmonie des anges)
- 22番「舟歌」(Barcarolle)
- 23番「帰り道」(Le Retour)
- 24番「つばめ」(L’hirondelle)
- 25番「貴婦人の乗馬」(La chevaleresque)
- ブルグミュラー25の練習曲の「練習する時のポイント」全曲紹介|まとめ
- ブルグミュラー25の練習曲【発表会】レベル別おすすめの曲
- 【ブルグミュラー25の練習曲】全て学ぶのにかかる期間
- 【ブルグミュラー25の練習曲】生徒・先生に人気のある曲は?
- 【ブルグミュラー25の練習曲】難易度と特徴を全曲紹介!発表会におすすめの曲|まとめ
ブルグミュラー25の練習曲【難易度】・【特徴】

「ブルグミュラー25の練習曲」
練習を始めるにあたって、それぞれの「特徴」と一般的な「難易度」(目安)ってちょっと気になるところだと思いますので全25曲を詳しくまとめていきますね。
| No. | 曲名 | 特徴/演奏ポイント | 難易度(★~★★★★★) |
| 1 | 素直な心 | レガート奏法の練習。歌うようになめらかに | ★ |
| 2 | アラベスク | 素早い指運び、16分音符。冒頭のリズム感が肝要 | ★ |
| 3 | 牧歌 | 優しい雰囲気。右手メロディをよく聴いて | ★ |
| 4 | 小さな集会 | 和音のバランス練習。表現豊かに | ★★ |
| 5 | 無邪気 | スラー・スタッカート対比、かわいらしく | ★ |
| 6 | 進歩 | アクセント・スラーの使い分け | ★★ |
| 7 | 清らかな流れ | 分散和音の流れ、手の動きを広く使う | ★★★ |
| 8 | 優美 | 歌うメロディ、伴奏音に気を配る | ★★ |
| 9 | 狩り | 跳ねるリズム、スタッカートの明確さ | ★★ |
| 10 | やさしい花 | 優しいタッチ、細かい表現力 | ★★ |
| 11 | せきれい | 細かい動き、両手のバランス | ★★★ |
| 12 | 別れ | 3連符やリズム表現。感情を込める | ★★★★ |
| 13 | なぐさめ | 左右のバランス、優しい音色 | ★★★ |
| 14 | スティリエンヌ | 踊るようなリズム、軽快感 | ★★★ |
| 15 | バラード | 堂々とした演奏、ストーリー性の表現 | ★★★ |
| 16 | あまいなげき | 静かな悲しみ、細やかな表現 | ★ |
| 17 | おしゃべり | 左手の連打・スタッカート | ★★★ |
| 18 | 気がかり | 強弱・アクセントの対比 | ★★★ |
| 19 | アヴェ・マリア | 美しい旋律の歌わせ方、柔らかな和音 | ★★★ |
| 20 | タランテラ | 速いテンポ、躍動感あるリズム | ★★★★ |
| 21 | 天使のハーモニー | 流れるようなフレーズ、繊細さ | ★★★★ |
| 22 | 舟歌 | 波を思わせる伴奏、歌うメロディ | ★★★★ |
| 23 | 帰り道 | 左右の違う奏法(レガートとスタッカート)のコントロール | ★★★★ |
| 24 | つばめ | 左手の跳躍、素早い動き。スワローが飛ぶイメージ | ★★★★ |
| 25 | 貴婦人の乗馬 | 堂々としたリズム、ペダリング、左右のバランス | ★★★★ |
難易度の目安と全体の特徴
難易度は★(初級)から★★★★(中上級)まで。
全体的に初級~中級への橋渡しとして最適な構成です。

すべての曲に標題(タイトル)がつき、イメージを持ちやすく「表現を学ぶ導入」として評価が高い素敵な曲ばかりです。
各曲は短く(~2分程度)、コンクールや発表会曲に選ばれることも少なくありません。
固有のテクニック(レガート、スタッカート、和音、シンコペーション、リズム変化、ペダル等)に特化しつつ、音楽性重視で書かれています。
ブルグミュラー収録曲の練習ポイント
強弱やアーティキュレーション、音色の違いに特に注意して練習しましょう。
聴く力・感じる力を養うことを意識して、美しい音楽に仕上げることが目標です。
アーティキュレーション(Articulation)とは
「音と音のつながり方・形のつけ方」を総称する言葉。
ピアノでのイメージ:レガート(なめらか)、スタッカート(切る)、テヌート(しっかり伸ばす)、アクセント(強調する)など、音をどう出すかを示す“演奏表現の指示”です。
例:楽譜に記号(スラー、ドット、アクセント記号)が書かれている場合、それらを意識すると音楽に豊かな表情が生まれます。
ブルグミュラー25の練習曲の「練習する時のポイント」全曲紹介

演奏のポイントや表現のコツをまとめたので、日々の練習やレッスン時の参考にしてください。
1番・「素直な心」(La candeur)
この曲はピアノ学習者が「最初に音楽的なレガート(なめらかに音をつなぐ)」を学ぶのにぴったりなやさしいメロディです。
明るく清らかで、タイトルどおり“まっすぐで素直な気持ち”が表現されています。
レガート(Legato)とは
「音と音を切れ目なく、滑らかにつなげて弾く」という奏法です。
前の音を離すときに次の音を同時に押さえて「素直に歌う」感覚。
スラー記号(弧線)や「レガート」と書いている時は、この奏法を意識します。
練習ポイント
- 音を切らず、なめらかにつなげて弾くレガート奏法を身につけましょう。
- 指がバタバタしないよう、1音ずつ丁寧にコントロールします。
- 曲全体でメロディーをやさしく、自然に歌う気持ちで弾きます。
- テンポ指定は速めですが、無理のない速さで丁寧に音をつなげましょう。
2番・「アラベスク」(L’arabesque)
明るく軽快。 モノクロ写真のような規則的な模様(アラベスク)をイメージできます。
右側に細かい16分音符が多く、リズムの粒ぞろいが聴きどころです。

発表会などではみんなで取り合いになるくらい子供たちに人気の曲です。
粒をそろえるとは
「粒(つぶ)」とは、「一つ一つの音の形や大きさ」のことです。
「粒がそろっている」というのは、どの音も同じくらいの強さ、音の長さ、はっきりさで均等に並んで聴こえることを言います。
練習ポイント
- 指の動きが速い16分音符が多いですが、1つ1つの音の粒が集まるように練習しましょう。
- まずはゆっくりとした速度で指を均等に動かす練習から始めます。
- 左手の和音が重くならないように。
- アクセントやスラー(つながる部分)の場所に注意し、メロディーや方向性を意識しながらみましょう。
3番・「牧歌(パストラル)」(La pastorale)
田舎や自然の穏やかな風景を感じさせる曲。
ゆっくり流れる旋律で、心が緩むような安心感があります。

ブルグミュラーコンクールでは「アラベスクが弾きたい!」と譲らない娘に
「この曲の方が点数取れると思うよ!」
と先生に全力で進められてこの牧歌を演奏しました。
結果、大好きな1曲になっています!
練習ポイント
- 曲のタイトルから“のどかさ”や“田園風景”をイメージすると歌いやすい。
- 右手のメロディーは穏やかに歌わせて、左手の伴奏リズムも軽やかに。
- 導入部やフレーズの切れ目はルバート(自然な揺らし)をつけても良い。
「ルバート(Rubato)」とは
ピアノをはじめとする音楽演奏の用語で、主にテンポを自由に伸び縮みさせる表現技法のことを言います。
曲に「歌心」や「語りかけ」の雰囲気を加えたい時に、とても大切な表現方法です。
4番・「小さな集会」(La petite reunion)
小さなパーティや子どもの集会の賑やかさが感じられる曲です。
右には3度の和音(隣り合う2音の和音)がたくさん含まれています。
練習ポイント
- 和音をひとつひとつ独立した音として、雑にならないようにきれいに響かせましょう。
- 左右の音量バランスや、強弱の変化に注意します。
- 曲の前半は慎重に、後半は落ち着いて演奏すると、曲の中の「集会の雰囲気」を出しやすいです。
5番・「無邪気」(Innocence)
シンプルでかわいらしいワルツ。
素朴な楽しさや、子どものはじけるような純粋な表現がされています。
練習ポイント
- 3拍子のリズム(ワルツ感)を大切に、「1、2、3」と心で聴きながら弾きましょう。
- 右16分音符は指を開きすぎず、きれいに粒を考えて演奏します。
- スラー(滑らか)とスタッカート(短く切る)部分の違いをハッキリ出しましょう。
スラー(slur)とは
意味は「その線でつながった音を、途切れずに滑らかに続いて弾いてください」という指示です。
「つながって歌う」イメージで、息を止めずに、穏やかな言葉をつなげるように演奏します。
スタッカート(Staccato)とは
意味は「一音一音を切り離して短く弾く」奏法のことです。
鍵盤を押した後、すぐ指を離して、「ポン、ポン」と歯切れよく弾きます。
音符の上や下に点(ドット)が付きます。
6番・「進歩」(Progres)
曲名の通り、「前進」や「成長」のイメージが感じられる元気な曲です。
スケール(音階)や異なる奏法が出てきて、発展段階のテクニック練習にぴったりです。
「ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ド」
と並べた音階のことを言います。
練習ポイント
- スケール(ドレミ…と続く音階)の響きを意識します。
- レガートとスタッカートの切り替えに注意し、フレーズごとに表現を変えます。
- 中間部の和音はとりあえずパッと正確に押さえられるように、手の位置移動も練習するとよいです。
7番・「清らかな流れ」(Le courant limpide)
水がすーっと流れるような爽やかな曲です。
右の分散和広がる特徴で、「流れる」感覚が心地よい。
練習ポイント
- 右手分散和音が“水の流れ”のように美しく聞こえるよう腕や手首の力で演奏します。
- 親指が強すぎないように、指の使い方と手首・腕の脱力を大切にします。
- ペダルは“音を伸ばすためだけでなく、響きを与えるため”に軽く使う。
8番・「優美」(La Gracleuse)
華やかで繊細な雰囲気、美しい装飾が印象的です。
スタイリッシュで流れるようなメロディライン。
練習ポイント
- 装飾音(ターンやトリル)は1音ずつ明確に、美しさと粒立ちを意識する。
- 指先だけではなく、腕全体を優しく使って響きを作ります。
- メロディは自然な会話のように、優美な表現を目指します。
9番・「狩り」(La chasse)
馬で狩りをするような、勇ましいリズムと躍動感のある曲です。
右手の跳ねる動きや和音の移動が目立ちます。
練習ポイント
- 右手のリズムは力強く、跳ねる感じを大切に。
- 和音の位置は手首の柔らかさを利用してスムーズに移動しましょう。
- 強弱やアクセントを加えて、勇敢な雰囲気が伝わるように演奏します。
10番・「やさしい花」(Tendre Fleur)
繊細さ・やわらかさを表現。
対位法(両手に独立した旋律)があり、2つの旋律の対話を意識する曲。
練習ポイント
- 右手・左手ともメロディ意識を持つ。どちらかが伴奏にならず、両手のバランスを丁寧に聴き分ける。
- 強弱「ピアノ」や「デリカート(繊細に)」に忠実に。各フレーズのアーティキュレーション(スラー・スタッカート)を明確に。
- 左手の和音は重くならず、“花が風に揺れるイメージ”で。
- 5〜8小節目・21〜24小節目など、片手ずつレガート&指使い確認を丁寧に。
- 装飾音のあとは、テンポが崩れないよう注意。
11番・「せきれい」(La Bergeronnette)
軽快な動き・和声の跳躍が特徴。
小鳥の軽やかな動きを思わせる。
練習ポイント
- スタッカートで「鳥の跳ねる様子」を表現。音が濁らないように指先を意識。
- 右手16分音符の粒立ちが大事。ゆっくり練習からスタートし、一定のテンポと音量バランスを保つ。
- 左手の伴奏は主張しすぎないが、「跳ね」のリズム感は損なわないように。
12番「別れ」(Adieu)
切なさ、寂しさを感じさせる旋律美があり、やや叙情的。
練習ポイント
- 3連符、シンコペーションのリズム正確さ・流れるようなレガートを心がける。
- 強弱表現を繊細に(寂しさや別れの情感を、音色で工夫)。
- フレーズの終わりで急いで切らない。“余韻”を大切に。
シンコペーションとは
本来の拍の強弱のパターンを意図的にずらし、弱拍を強調したり、強拍を弱くしたりするリズム技法のことです。
タイや休符などによって一時的に変化させていることが多いです。
13番「なぐさめ」( Consolation)
穏やかな優しさ、癒しを感じる曲調。
練習ポイント
- 右手メロディの歌わせ方に注意。自然なフレージング(息継ぎのような間や盛り上がり)を意識。
- 弱奏「ピアノ(p)」を保ちながら、響きを豊かに。
- 左手の伴奏は伸びやかに。音が途切れないようペダルも工夫する。
14番「スティリエンヌ」(La Styrienne)
踊りの曲調、リズムの楽しさ。民謡的な活気があります。
練習ポイント
- 付点リズム・スタッカートの歯切れ良さを強調。
- 各フレーズのアクセントや和音跳躍を、手首の柔らかさで表現。指だけに頼らない。
- 曲の途中、強弱変化や表情変化もはっきりと。
15番「バラード」(Ballade)
叙事詩の語り手のような、力強さや物語性を感じさせる曲。
練習ポイント
- 堂々とした響きで、メロディの主役感を出しましょう。
- 急激な強弱変化でドラマティックに。曲中の山場をしっかり作るため、前後の雰囲気を弾き分ける。
- 左右のバランス、伴奏音の安定感を大事に。
16番・「あまいなげき」(Douce plainte)
しっとりした短調のメロディが印象的な小品。細やかな感情表現が求められます。
練習ポイント
- 長い2分音符は“歌う音”を意識し、左手の分散和音の動きと音量バランスを丁寧に。
- クレッシェンド・ディミヌエンドの細かな変化に繊細に反応。
- メロディの受け渡し(左右でつなぐ箇所)は滑らかさ重視で。
- 終わりは音を残して消えるように余韻を大切に。
17番「おしゃべり」(La Babilarde)
軽やかでせわしなく、おしゃべりが止まらない様子をリズミカルに表現します。
練習ポイント
- 指先をしっかり使い細かな音を粒立てて。
- スタッカートとレガートの対比、リズムの安定を心がける。
- 1小節を塊で捉え、一定感を出すとテンポの乱れがなくなります。
18番「気がかり」(Inquietude)
不安げな動きをもつ速いテンポの作品。
無窮動的な右手+左手の受け渡しが特徴的です。
練習ポイント
- 右手16分音符の粒を揃えて、焦らず全体の流れを止めないこと。
- 左手の和音は歯切れよく、スタッカートの軽やかさに注意。
- 曲中の“動きの変化”(転調やクレッシェンド)で速度や表情の付け方にメリハリを。
19番「アベ・マリア」(Ave Maria)
シンプルで美しい合唱のようなハーモニーと、優しい祈りの響き。
練習ポイント
- 4声のハーモニーを意識(各声部のバランス注意)。
- レガートを意識して、メロディの“歌”を途切れずつなげる。
- 長いフレーズごとに自然な“ブレス”を感じて演奏(合唱を思い浮かべて)
20番「タランテラ」(La Tarentelle)
イタリア風の舞曲でスピーディー、小気味よいリズムが特徴。
練習ポイント
- 和音が重くなりすぎないように、軽妙さを大事に。
- スタッカート、フォルテ/ピアノの対比で緩急を付ける。
- 左手は跳ねすぎず、リズムをキープ、跳躍部分は反復練習を。
21番「天使のハーモニー」(L’harmonie des anges)
透き通るような分散和音と、静かな響きが天使のイメージ。
練習ポイント
- 分散和音をなめらかに、左右ともにフレーズを一体化する意識。
- 親指が強くなりすぎないようにタッチのコントロール。
- ペダルは響きを整えるために、最小限で使うと美しい。
22番「舟歌」(Barcarolle)
ゆったりと揺れる舟を思い起こさせる、波を感じるリズムが魅力。
練習ポイント
- フレーズを息長く“歌う”こと、途中で止まらない。
- 伴奏は静かに波のような表現を。
- テンポが遅くなりすぎないよう要注意。
23番「帰り道」(Le Retour)
和音連打とフレーズごとの表情づけがポイントの、やや技巧的な練習曲。
練習ポイント
- 和音を連打するためには手首の脱力が不可欠。
- ゆっくり練習し確実なリズム、安定した響きを身につける。
- ペダルは濁らせないよう最小限に。
24番「つばめ」(L’hirondelle)
跳躍を駆使した、スピード感と軽さがツバメを想起させます。
練習ポイント
- 横方向を意識した手の移動(跳躍)の練習。腕は“上”でなく“横”へ素早く。
- 跳躍部分だけを抽出して何度も練習。
- 全体に切れ味よく流れるように。
25番「貴婦人の乗馬」(La chevaleresque)
有名な締めくくりの1曲。華やか、優雅で力強い疾走感。
練習ポイント
- 最初は軽快にリズム重視、優雅な部分とフィナーレの切り換えを明確に。
- 途中のフレーズやセクションごとの雰囲気を変える意識。
- 音階部分や跳躍のリズムを丁寧に鍛えること。
ブルグミュラー25の練習曲の「練習する時のポイント」全曲紹介|まとめ
難易度が比較的優しい前半1~10番のポイントは
- メロディと伴奏のバランス、強弱・アーティキュレーションの明確な弾き分け。
- タイトルの情景や雰囲気を“イメージ”しながら練習すると、自然と音楽性が高まります。
- 指使いや手首、腕の使い方を「無駄なく・脱力しながら」工夫。
さらに後半(10番~25番)は
- より複雑なリズムや、和音・跳躍・ペダルテクニックなど中級レベルに近い課題が増えます。
- 各曲のタイトル、ストーリー性を意識することで「楽譜の指示以上の表現」が育ちます。
練習のコツの共通原則:
- 楽譜の強弱・指番号・スラー、スタッカートをよく確認。
- 一定のテンポにとらわれず、きれいな音と安定した運指を優先。
- 曲のタイトルや情景に合った音色・表現を目指す。
このあたりを意識して練習に取り組むと良いと思います!

「1曲ごとに練習課題が明確であり、音楽性の基礎を学びながら表現力も身につく教材」として、ぜひじっくり取り組んでください。
ブルグミュラー25の練習曲【発表会】レベル別おすすめの曲

初級(ピアノ学習初期~小学校低学年)
中級(ブルグミュラー集の中程~小学校高学年)
上級(指使い・表現力ともに上達した学習者)
【ブルグミュラー25の練習曲】全て学ぶのにかかる期間

ブルグミュラー25の練習曲を全て学ぶのにかかる期間について丁寧に説明します。
まず、ブルグミュラー25の練習曲は、ピアノの初級から中級くらいのレベルの人が取り組む教本です。
全部で25曲あり、それぞれ難易度や内容が少しずつ違うため、練習期間は人それぞれですが、おおよその目安があります。
練習曲全体を終わらす期間のめやす
一般的には「1年半~2年」くらいかかると言われています。
これは1曲ごとにだいたい3~4週間じっくり練習し、曲をしっかり仕上げていくペースです。
「1年~2年」というのはあくまでも目安で、集中して練習すれば1年で終わる人もいます。
例えば1曲を2週間以内に仕上げるようなハイペースで取り組めば、1年以内に25曲弾けるようになります。
逆にゆっくり自分のペースで弾く場合はもっと時間がかかることももちろんあります。
初めての曲は特に時間がかかりますし、難しい曲は練習にも集中力と回数が必要です。

早ければいいというものでもありませんし、1曲ずつ丁寧に仕上げていきましょう!
効率よく終わらせるためのポイント
- 毎日30分~1時間の練習を継続することが大切
少しずつでも毎日取り組めば、上達は確実に早くなります。 - 曲によって難易度や苦手な部分が違うので、そこを重点的に練習する
弾きにくいところを集中して繰り返すことで、全体の上達がスムーズです。 - 無理に急いで次の曲に進まず、できるだけ「仕上げる」感覚で練習する
発表会などの目標がある場合は、特に丁寧に練習しましょう。
ブルグミュラーにかかる期間|まとめ
ブルグミュラー25の練習曲は、約1年半~2年程度かけてじっくり取り組むことが多いです。
早い人なら1年以内に終えることも可能ですが、基礎をしっかり身につけながら無理なく進めることが大事です。
毎日継続して練習し、1曲ずつ着実にマスターしていくペースで進めてください。
このように、目標やペースに応じて期間は変わるので、自分に合った練習計画を立てて楽しく取り組むのが成功の秘訣です。
【ブルグミュラー25の練習曲】生徒・先生に人気のある曲は?

ブルグミュラー25の練習曲、どの曲も勉強になる素敵な曲ばかりですが、なかでも特に人気の曲があります。
これらはピアノレッスンや発表会、コンクールなどでもよく選ばれている名曲です。
何かの参考になるかもしれないので、紹介しておきますね!
ブルグミュラーの特に人気が高い定番曲
1番「素直な心」
曲集の冒頭を飾るやさしいメロディ。
レッスンの最初や発表会のデビュー曲として選ばれることが多いです。
2番「アラベスク」
明るく軽やかなリズムと耳なじみの良さで、ブルグミュラーの中でも圧倒的な人気を誇ります。
5番「無邪気」
シンプルながら可愛らしさが際立つ作品で、子どもの発表会曲としても人気です。
8番「優美」
きらきらとした美しい旋律とテクニックのバランスから、特に女の子に人気があります。
10番「やさしい花」
繊細な音色と左右の旋律の対話が特徴的で、多くの生徒が挑戦する1曲です。
14番「スティリアの女」
踊るようなリズムが楽しい曲で、会場の雰囲気も華やかになります。
15番「バラード」
劇的な強弱や物語性があり、発表会やコンクールでも注目を集めます。
18番「心配」
スピード感とストーリーのある曲想から、成長の節目に選ばれることが多いです。
19番「アベ・マリア」
合唱のような和声の美しさが大人にも人気で、しっとりとした演奏を楽しめます。
20番「タランテラ」
舞曲風の華やかさとテクニックを披露できる発表会向けの定番曲です。
21番「天使の声」
分散和音の響きが美しく、大きなホールでも映える1曲です。
25番「貴婦人の乗馬」
華やかで力強いエンディングを飾る、最も有名なフィナーレ曲。
締めくくりや発表会のラストに大人気です。
これらの曲以外にも、美しいメロディや印象的なリズム、個性豊かな楽曲がそろっているため、
選曲の際は自分の好きな雰囲気や得意なテクニックで選ぶのもおすすめです。
ピアノの先生が好きなブルグミュラーの曲は?
ピアノの先生としてブルグミュラー25の練習曲を教える際、

「教えていて楽しい」

「教えやすい!」
と感じる曲はいくつもあるそうです。
ここでは実際に
- 娘の師匠であるピアノの先生
- わたしが時々習うオンラインレッスンのピアノの先生
- ピアノ講師をしているお友達
この3人に聞きこんできましたので、指導現場の声や教材の特徴を踏まえて、特におすすめの曲をまとめてご紹介します。
教えていて楽しい曲
- 2番「アラベスク」
- 明るく軽快なリズム、子どもも親しみやすいメロディ。生徒が曲の世界観をイメージしやすく、リズムや表現の指導が楽しい1曲です。
- 14番「スティリアの女」
- 踊りのリズムやアクセント、強弱の工夫がたくさん。生徒の性格が表れやすく、一緒に物語を作るように教えられる曲です。
- 25番「貴婦人の乗馬」
- 楽しくエネルギッシュに仕上げていく達成感。多くの生徒が憧れる、発表会やコンクールの華やかな一曲です。
教えやすい(効果が分かりやすい・ポイントが明確)
- 1番「素直な心」
- レガート奏法、左手伴奏の基礎として理想的。歌う心や音のつなぎ方をじっくり伝えられます。
- 3番「牧歌」
- ゆったりとしたリズム、旋律のバランス、音価のコントロールが学びやすく、先生側も生徒の成長を感じやすい曲です。
- 5番「無邪気」
- シンプルながら表情付けやスタッカートを練習しやすく、特に初心者に「音楽の面白さ」を知ってもらえる曲です。
- 10番「やさしい花」
- 左右の対話や細やかな表現を自然に指導できるので、音楽的な会話の楽しさを伝えやすいです。
先生からみたポイント

タイトルやイメージがハッキリしているので、
“曲にストーリーを持たせて一緒に考えながら教えられる”
曲が多いです。

初心者の土台作りから、楽しく音楽表現を深める段階まで段階的に指導できるのがブルグミュラー25の強みです。

「手の動かし方」「響き」「強弱のつけ方」「ペダル」など技術目標が明確な曲が揃っています。
と言う事でした!
やっぱりブルグミュラー25の練習曲は勉強になるんですね!
【ブルグミュラー25の練習曲】難易度と特徴を全曲紹介!発表会におすすめの曲|まとめ

ブルグミュラー25の練習曲は、1曲ずつ異なるテーマやテクニックが書かれており
ピアノ初級~中級への橋渡しとして最適な教材です。
全曲に情景や物語が込められていて、表現力も身につきます。
困難度の目安
-
★(初級)~★★★★(中上級)まで、段階的にレベルアップできる構成
-
前半(1~10番)は比較的穏やかな表現、後半になるほどテクニックや力が求められます
全曲の特徴&おすすめポイント
人気・おすすめ曲
| 人気曲 | 特徴・おすすめポイント |
|---|---|
| 素直な心 | まっすぐなメロディ、レガート奏法初歩 |
| アラベスク | 遊んで楽しい軽快なリズム、指運び練習に |
| 邪気なし | シンプルで明るいワルツ、スタッカートの導入 |
| 優美 | きらびやかな旋律、美しい表現を学べる |
| やさしい花 | 左右のメロディー、繊細なバランス |
| スティリエンヌ | 踊りのリズム、躍動感が楽しい |
| バラード | ストーリー性・ドラマチックな響き |
| タランテラ | テンポが良く、華やかで発表会向き |
| 貴婦人の乗馬 | 華やかなフィナーレ、技術も表現できる |
効率よく進めていくポイント
-
前半のやさしい曲で基礎をしっかり固め、好きな曲や目標になる曲を見つけて挑戦していくのがステップアップの近道です。
-
どの曲にも「学びの課題」と「音楽の楽しさ」が詰まっているので、ご自身のペースで進めてOKです。

ブルグミュラー25の練習曲は、発表会やコンクールでも色とりどりの名曲があり、練習しがいのある教材です。
ぜひ練習に取り組入れてみましょう!!